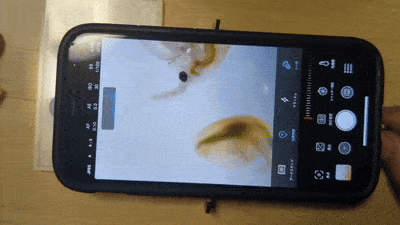今まで知っていましたか?花粉の面白いあれこれ
Share
冬の寒さからだんだんと暖かくなるにつれて毎年話題になるのが、花粉!

風にあおられたスギ花粉が飛散して黄色い霧のように流れている動画を見たことも多いはず。花粉症の人にとってはつらい季節ですね。。。
この嫌われ者の花粉ですが、植物にとっては大事ないのちの営みなんです。今回はこの花粉について記事を書いてみました。
1.花粉を観察してみよう
①スギ花粉
スギ花粉の観察の仕方は簡単です。杉の木から直接花粉を採取しても良いですし、近くに杉の木がなければ窓や車のボディに付いた花粉から採取しても良いです。
▼ミクロハンターレンズで花粉を観察している様子

▼割れた花粉

上の写真は製品ユーザー様が撮影したもの(投稿元:とるすといさん)。
スギ花粉は水に濡れるとパックリと割れてまるでパックマンみたいな形になります。
花粉が鼻の粘膜についも同じように割れ、花粉内のアレルゲンが流れ出します。これが体内に吸収されることでアレルギー反応が起こります。
|
▼スギ花粉の観察実験動画(約1分) ※ミクロハンターキットLiteで観察 |
②オシロイバナの花
オシロイバナは比較的大きな花粉なので、観察しやすい花粉の1つです。黄金色に輝く花粉はまるで宝石のように本当に綺麗です!
▼オシロイバナの花
|
▼観察実験の動画(約1分) ※ミクロハンターキットPLで観察 |
③苺の花
苺の花粉は米粒のような形をしていますね。ちなみにこの時は、セロハンテープに花粉を付けて観察しました。

|
▼苺の花粉観察実験動画(約45秒) ※ミクロハンターキットPLで観察 |
2.花粉症を引き起こす植物
よく話題になるのはやはりスギ花粉ですが、スギ以外にも花粉症になる花粉はたくさんあります。花粉症になりやすいのは主に風に乗せて花粉を飛散させるタイプの植物です。
①花粉症を引き起こす木の代表例
| 名前 | ハンノキ | スギ |
| 写真 |  |
 |
| 飛散時期 | 1~4月頃 (冬~春) |
3~5月頃 (春頃) |
| 主な地域 | 日本全域 | 本州 |
| 名前 | ヒノキ | クヌギ |
| 写真 |  |
 |
| 飛散時期 | 3月~5月 (春頃) |
4月中旬~5月下旬 (春頃) |
| 主な地域 | 本州福島地方~九州屋久島の山地 | 日本全域の日当りの良い山野 |
| 名前 | イチョウ | コナラ |
| 写真 |  |
 |
| 飛散時期 | 4月〜5月頃 (春頃) |
4月〜5月頃 (春頃) |
| 主な地域 | 日本全域 | 北海道南部から本州、四国、九州の全域 |
| 名前 | ケヤキ | シラカバ |
| 写真 |  |
 |
| 飛散時期 | 4月〜5月頃 (春頃) |
4月中旬〜6月初旬頃 (春~初夏) |
| 主な地域 | 本州、四国、九州の比較的温暖な地方 | 北海道、本州(福井・岐阜県以北) |
②花粉症を引き起こす草の代表例
| 名前 | カモガヤ (イネ科) |
オオアワガエリ (イネ科) |
| 写真 |  |
 |
| 飛散時期 | 5〜8月 (春~夏) |
5〜8月 (春~夏) |
| 主な地域 | 日本全域 | 日本全域 |
| 名前 | ヨモギ (キク科) |
ブタクサ (キク科) |
| 写真 |  |
 |
| 飛散時期 | 8〜10月 (夏~秋) |
8〜10月 (夏~秋) |
| 主な地域 | 日本全域 | 日本全域 |
③特定の人に花粉症を引き起こす植物
風によって媒介される花粉を持つ植物と異なり、虫によって媒介される花粉を持つ植物は花粉症を引き起こしにくいです。花粉が風で飛散する訳ではないので遠くに飛ばないからです。しかし、そのような植物であっても仕事として日常的に触れる場合はやはり花粉症になってしまう事があります(以下がその例)。
| 梅 | バラ | イチゴ | リンゴ |
 |
 |
 |
 |
| 2〜3月 | 3〜5月 | 4〜5月 | 4〜5月 |
3.なぜ花粉がアレルギーになるの?
体に無害なはずの花粉でなぜアレルギーを起こすんでしょうか?
これにはからだの免疫システムが密接に関わっています。私たちの免疫システムは非常に優秀なのですが、時々誤作動を起こす事もあり、これが非常に厄介なのです。
これにはからだの免疫システムが密接に関わっています。私たちの免疫システムは非常に優秀なのですが、時々誤作動を起こす事もあり、これが非常に厄介なのです。
①花粉がアレルギーを起こす流れ
- 目や鼻などに花粉が侵入する
- Bリンパ球が間違えて花粉を敵と認識すると、敵である花粉を排除するために抗体(IgE抗体)を製造する
- マスト細胞の周りに抗体がくっつく
- マスト細胞の周りの抗体に花粉が付くと、スイッチが押されたかのようにマスト細胞からヒスタミンという物質が放出される
- ヒスタミンの影響で炎症、涙、くしゃみなどが発生し、花粉を排除する
|
【解説】免疫システムの用語 ・Bリンパ球:免疫細胞である白血球の一種。抗体を作る働きをする。B細胞とも呼ばれる。 ・マスト細胞:免疫細胞の一種。気管支、鼻粘膜、皮膚など外界と接触する組織の粘膜や結合組織に存在する。肥満細胞とも呼ばれる。 |
②なぜ昔と比べて花粉症が増えたの?
これには以下のような様々な原因が複雑に絡み合っていると考えられています。
- 偏った食生活や添加物の多い食事
- 自律神経を乱す不規則な生活、睡眠不足や運動不足
- ストレスの多い生活
これらが原因で免疫システムが誤作動を起こすことが増えたということでしょうか。
あと、先進国で共通しているある現象があるそうです。それは「感染症が減っている場所ではアレルギーが増えている」という現象。つまり衛生環境が整っている場所ほどアレルギーが増える、ということですね。いい事なのか悪い事なのか・・・。
個人的には、なんでも「除菌、抗菌、消毒、殺菌」「汚いから触らない!」と過敏になりすぎる事で免疫機能を向上させる大事な機会が減っているのかなとも思います。いっぱい土をいじったり動物や昆虫と戯れたりして、でも必要な時にはちゃんと手洗い、うがいをする、そんなメリハリが大事なのかなと。
4.花粉にまつわる自然現象
▼花粉光環

花粉症の人からは「魔のサークル」と言われています。大量の花粉が空気中に舞うと発生する自然現象で、太陽の周りに何重にも虹色の輪っかが見られます。花粉の粒子によって太陽の光が干渉&回折する事で見られる現象です。
|
【もっと詳しく】光の干渉と回折とは? 干渉は複数の光の波が重なって、互いに強くなったり弱くなったりすること。一方、回折は光の波が障害物にぶつかった時に、その障害物を回り込んでいくことです。 |
5.そもそも花粉って何?
①花粉が出来てから受粉するまでの過程
花粉の中には人間でいうところの精子の材料が入っています。つまり子孫を残すために必要なものということ。その花粉が出来るまでの過程をイラストにしてみました。

※小胞子(未熟な花粉)から成熟した花粉になるまでの成熟過程は、裸子植物と被子植物で違うそうです(参照:筑波大学サイト)
あの花粉に植物が子孫を残すためのDNAが入っている、と思うとなんだか神秘的なものに思えてきますね!
|
【ちょっと補足】花粉の精細胞について 裸子植物と被子植物で精細胞の呼び方が変わる事があります。 ・裸子植物
裸子植物の精細胞には、なんと人間と同じ鞭毛がついていて自分で動き回ります。そのため精子と呼ばれることも。
・被子植物
被子植物の精細胞には鞭毛がないため、精核と呼ばれることもあります。 |
6.スマホで本格顕微鏡ミクロハンターレンズ
いかがでしたか?今まで知らなかった花粉の面白い話はありましたでしょうか?
顕微鏡と絡めたテーマで引き続きブログマガジンを書いていきますのでよろしくお願いいたします!
最後に「ミクロハンターレンズ」もぜひ紹介させて下さい。