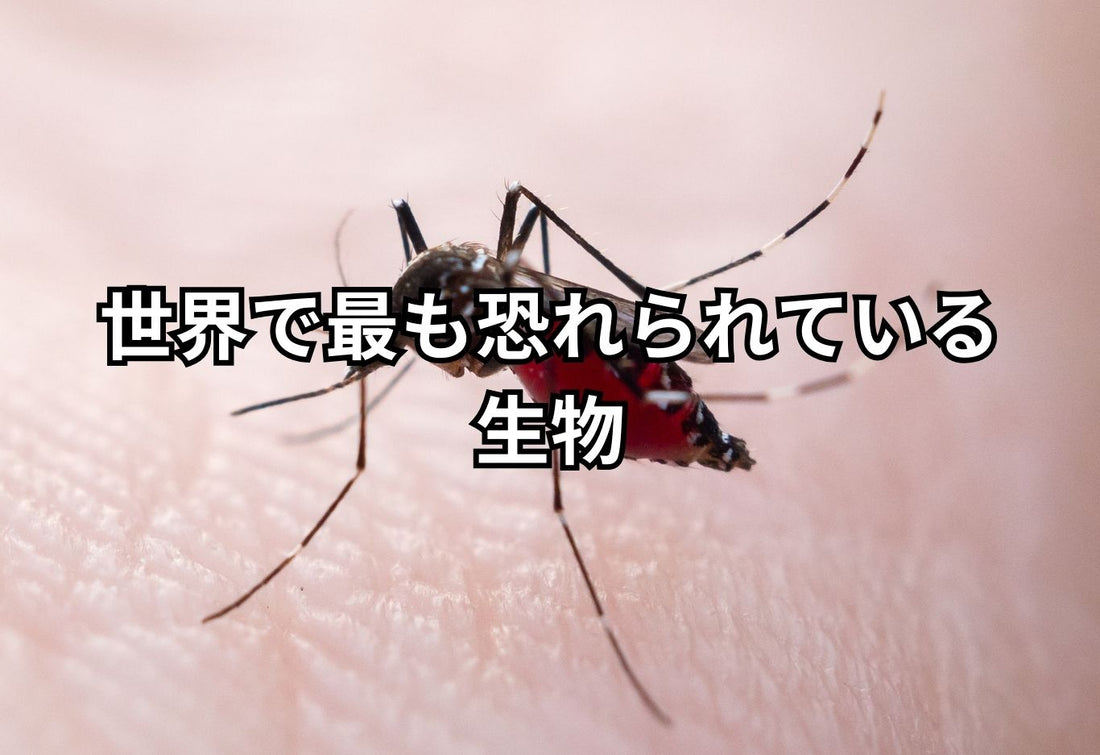
「蚊」の不思議あれこれ、驚くべき生態と対策
Share
はじめに

夏になると必ず出てくる「蚊」。寝ている時に耳元で「プーン」と鳴かれると、うるさくて眠れないですよね。でも、この小さな存在を侮ってはいけません。なんと世界で一番人を殺している生き物は蚊なんです。
この記事では、蚊の生態や成長過程、雄と雌の違い、顕微鏡での観察、最新の遺伝子組み換え研究、そして日常でできる蚊よけ・虫よけ対策を、できるだけわかりやすく紹介します。
地上で最も人間を殺している生き物は?
以下の図はgatenoteからの統計を図にしたもので、数字は各生物によって殺される年間の死者数です。

ライオンやサメよりもはるかに危険って、ちょっと意外ですよね。その理由は、蚊がたくさんの感染症を運んでくるからです。
蚊の生態をのぞいてみよう
蚊の成長のサイクル

蚊は「卵 → 幼虫(ボウフラ) → 蛹(オニボウフラ) → 成虫」というサイクルで成長します。少しの水でも卵を産めるので、人の暮らしにとても身近な存在になっています。
①蚊の卵

蚊は水のたまる場所に卵を産みます。蚊の卵は長さは約0.5mm程度、乾燥に非常に強く、水がなくなっても長期間乾燥に耐えることができます。そして雨水がたまると一斉に孵化して大量発生することも。卵は数日で孵化し、幼虫のボウフラになります。
②ボウフラ(幼虫)

水たまりや植木鉢の受け皿などにいる、うねうね動いている小さな生き物、それがボウフラです。水の中で呼吸管を水面に出しながら生きていて、微生物などを食べて成長します。
ボウフラをモバイル顕微鏡で観察
(35秒)
↓ ↓ ↓
(ミクロハンターキットLiteで観察)
③オニボウフラ(蛹)

蚊の蛹(さなぎ)は頭に付いた二つの吸気管が鬼の角に見えることから、オニボウフラとも呼ばれています。コンマ型の形をしていて、水面近くでクルクル動き回ります。そして危険を感じると水底に潜っていきます。この時期は食事をせず、数日間かけて羽化の準備をしています。そして殻を割って、大人の蚊として空へ飛び立つのです。
オニボウフラをモバイル顕微鏡で観察
(33秒)
↓ ↓ ↓
(ミクロハンターキットLiteで観察)
④成虫
蚊の成虫は体長3~7mmほどで、細長い体と長い脚、針のような口吻(こうふん)が特徴です。

蚊の雄と雌の違い
-
食性の違い
実は、血を吸うのは雌だけです。雌は卵を産むために血液中のタンパク質を必要とするんですね。一方で雄は花の蜜や樹液を食べて生きています。つまり、普段「かゆい!」と思わせるのは雌だけ、というわけです。
- 体の違い(雄と雌の見分け方)

蚊はどうやって血を見つけるの?
蚊は色んな感覚を複合的に使って餌にありつきます。蚊が持つ感覚器官について見ていきましょう。
4つの感覚器官
①嗅覚

蚊は最初に触角を使って、息に含まれる二酸化炭素の匂い、汗の成分(乳酸・アンモニア・脂肪酸など)、皮膚に入る常在菌が発する匂い、などをかぎつけ、餌になりそうな対象を探し始めます。蚊の嗅覚は非常に優れており、数十メートル離れた場所からも感知できます。
感知距離:~50メートル
②視覚

蚊の目は悪く、細かくは見えません。また色を認識することもできません。しかし、動きや色のコントラストを認識できます。そのため黒や濃い色の服は蚊に狙われやすいです。匂いである程度標的に近づき、その後視覚で判断してさらに近づきます。
感知距離:~10メートル
③熱感知器官

蚊には温度感受性TRPチャネル(TRPA1)という、熱を感じる受容体が触角にあります。餌となる標的にたどり着くと、今度は熱を感知しながら柔らかい皮膚を探し、血を吸います。
④聴覚
雌は聴覚が発達していません。一方、雄は聴覚が発達しており雌の羽音(約400Hz前後)を聞き分けて、交尾の相手を探します。私たちが嫌いな「プーン」という音は、蚊にとっては大事なラブコールなのかもしれません。
雄も雌も人間や動物の発する音を頼りに近づいてくることはありません。
どの感覚が優位?
上記の説明通り、圧倒的に優位なのは「嗅覚」です。
実はいつも血を吸う訳じゃない?
血を吸うのは雌だけ、というのは有名な話です。でも実は、その雌ですらいつも血を吸って生きている訳ではありません。
雌の蚊も雄と同様、普段は樹液や果汁、花の蜜を餌として吸っています。血を吸うのは「交尾後の産卵を控えた雌」だけです。
蚊が活発になる時の条件

下の2つの条件が揃うと蚊は活発に活動し始めます。
- 雨が降って水たまりが増える時
- 気温が25~30度
逆に言うと以下の時には蚊は不活性になります
- 少雨傾向
→産卵場所になる水たまりが蒸発
→ふ化・成長できない - 猛暑
→蚊は気温35度以上で動きが鈍る
夏の暑さが過酷だと蚊も夏バテで元気がなくなり、人を刺すことも少なくなります。
しかし、安心できません。
蚊の卵は乾燥に非常に強く、なんと産卵から1ヵ月経っても雨が降れば、ふ化します。
そして、秋頃に気温が落ち着いたころに「大発生」、なんてこともあり得るのです。
蚊は雨に濡れてもなぜ大丈夫なの?
蚊が雨に濡れても飛べる理由や、水に浮かべる理由はこちら・・・

蚊を叩き潰すと手に残る跡、これに秘密があります。

セロハンテープを密着&張り付けて採取します

蚊の跡がセロハンテープに移りました。このテープを折って張り合わせ、簡易のプレパラートの完成です。

スマホ用顕微鏡レンズMH-X250(光学250倍)をスマホに装着し、観察してみます

スマホ画面に映る羽のようなもの、それが蚊が濡れない秘密の正体です

実はこの鱗粉が羽や足など体中にくっついていることで、水を弾いているんです。面白いですね!
蚊の鱗粉やドクドクと脈打つ心臓を観察した動画はこちら!
↓ ↓ ↓
(ミクロハンターキットX250で観察)
蚊の種類
世界には3500種類以上の蚊が存在していると考えられており、そのうち日本には約100種類が生息しているようです。しかし、そのうち人の血を吸うのは国内ではたった20種。
代表的な日本の蚊の種類
- ヒトスジシマカ(ヤブカ)
- アカイエカ
- チカイエカ
蚊に刺されるとなぜ痒くなる?痒みの解消方法

蚊に刺された箇所はかゆみが出てきますよね。このかゆみの原因は何でしょうか?
蚊が血を吸う際に抗凝血作用物質(血が固まることを防ぐもの)を含む唾液を最初に注入するのですが、この唾液によってアレルギー反応が起き炎症が生じて痒くなるのです。
「血は少しくらい分けてあげるから、痒いのだけはやめてくれ!」と言いたくもなりますね。
痒くなったら、少しでもかゆみを早く抑える方法はないのでしょうか?
市販のかゆみ止め薬以外の方法を考察したいと思います。
熱で温めるとかゆみが消えるって本当?

(出典:Amazon 痒み止めペン)
SNSでは「蚊の毒素は43度以上で不活化される」という情報が拡散されて話題になっていたそうです。痒み止めペンなんているものも市販されています。
まずかゆみが消える理由として以下のような根拠が挙げられます
- 蚊の唾液には様々なタンパク質が含まれていますが、これが50度前後で変質する
- 熱刺激によって神経伝達が弱まってヒスタミンの分泌自体を抑えられる
一方で、以下のように反論する専門家います。
- 炎症で痒くなっているのだから、温めるのではなく冷やすべき
- 熱によって火傷をする可能性があり危険
どちらの言い分も理にかなっていると思います。
かゆみは個人差があるので、十分試す価値はありますね。
ただし、温熱療法をする際は以下の点に気を付けてください。
- 長時間熱を加えないようにして火傷に気を付ける
- 40度以下の温度で温めると痒みが強くなり逆効果になる可能性がある
ポイズンリムーバーは効果ある?

(出典:Amazon ポイズンリムーバー)
結論から言うと、蚊の痒みに対するポイズンリムーバーの医学的な効果は実証されていないようです。そもそも虫刺されの痒みに対するポイズンリムーバーの研究報告自体が存在しないとか。
ただし、効果がないわけではなく、実際に使用した人の中には「効果があった」という人も一定数存在するので、こちらも試してみる価値はあると思います。
ポイズンリムーバーを使用する際の留意点
- 刺された直後に使用する(直後でないと毒液を吸い出せない)
- 効果には個人差がある
もう逃がさない、蚊を叩く時のコツ
-
飛んでいる蚊を倒すコツ

プ~ンと近づいてくる蚊、こんにゃろう!と叩き潰そうとするもスル~スル~とうまくかわされて逃してしまう事はよくないでしょうか?
逃がしにくい叩く時のコツがあるのを皆さんはご存知ですか?
それは、「上下方向からパチン!と叩くこと」。横からパチンではなく、上下にパチンと叩くのがポイントです。
なぜなら、蚊は標的に近づく時に、上下に大きく揺れながら右や左に移動し狙いを定めてくるからです。
-
壁にとまっている蚊を倒すコツ

蚊は壁にとまっているときは上を向いるため、飛び立つときは上方向に動きます。そのため、頭の方向からゆっくりそ~っとある程度近づいたら一気に叩き潰すと良いです。
感染症を媒介する蚊
蚊が運ぶ感染症の例

蚊が怖いのは、単なる「かゆみ」ではなく、命に関わる病気を広げることです。
-
マラリア:毎年20万人以上が亡くなる病気。熱帯地域で大問題になっています。
-
デング熱:発熱や激しい痛みを伴い、重症化すると命に関わります。
-
ジカ熱:妊婦が感染すると胎児に小頭症のリスクがあります。
-
黄熱や日本脳炎:ワクチンがあるものの、発症するととても危険。
「世界で一番人を殺している生き物」と言われるのも納得ですね。
ちなみに日本国内で蚊が媒介する感染症による死亡例は、過去には日本脳炎やデング熱で発生しましたが、予防接種の普及や国内での感染が減ったことで、現在では稀です。

※2024年1月から4月までにWHOに報告されたデング熱患者の地理的分布
(WHOの世界デング熱サーベイランスシステムに統合されている103カ国のみ表示)
ただし、温暖化の進行により環境が変化しマラリアなどの新たな感染症が広がる可能性もあるため今後の動向に注意が必要です。
蚊は血を吸うだけなのになぜ病気を媒介するの?
実は蚊は血を吸う時に、血管を広げて血を固まりにくくするためにまず唾液を注入します。この唾液に病原体が含まれていると、刺された人は感染してしまうのです。
遺伝子組み換え蚊って知ってる?

最近は遺伝子組み換え蚊の研究も進んでいます。遺伝子を改変した雄の蚊を自然界に放すと、雌と交尾して生まれる子孫が成虫まで育たず、蚊の数を減らすことができます。
ブラジルやアメリカではすでに試験的に導入されていて、デング熱やジカ熱の拡大を抑える効果が期待されています。薬や殺虫剤だけに頼らない、新しい対策として注目されています。
一方遺伝子を人為的に組み替える為、倫理的な課題があります。
今日からできる蚊よけ・虫よけ対策
発生源をなくす
- 植木鉢の受け皿の水をこまめに捨てる
- バケツやタイヤなど、雨水のたまるものを放置しない
- 排水溝を定期的に掃除する
蚊よけグッズを使う
- 虫よけスプレー:ディートやイカリジン入りが効果的
- 蚊取り線香や電気蚊取り:部屋全体を守るのに便利
- 蚊帳や網戸:昔ながらですが、物理的に防ぐのが一番確実
ちょっとした工夫
- 足の裏をアルコールティッシュで拭く
→常在菌は足裏に密集しており、除菌する事で蚊の誘引物質を減らせます - 汗をかいたら早めに拭く
- 黒っぽい服を避けて明るめの単色の服を選ぶ
- なるべく肌を出さない(長袖・長ズボン)
こうした小さな工夫だけでも、蚊に刺される回数はかなり減らせます。
まとめ
蚊は小さな体でありながら、世界で一番人を殺している生き物です。
- 血を吸うのは雌だけ、雄は花の蜜を食べて生きている
- 嗅覚や視力、熱感知器官を駆使して人を見つける
- 遺伝子組み換え蚊の研究も進んでいる
- 蚊よけ・虫よけ対策を日常生活に取り入れるのが大事
蚊は身近な存在だからこそ、正しく知って備えることが大切です。今日からできる小さな対策で、自分や家族を守っていきましょう。
★スマホで本格顕微鏡ミクロハンターレンズ
最後に「ミクロハンターレンズ」もぜひ紹介させて下さい。

ミクロハンターレンズは、指先サイズでたった1g以下。しかし、その小ささからは信じられない光学性能を有します。思い立った時にさっと取り出して、どこででも本格派なミクロ探検を可能する製品として開発されました。
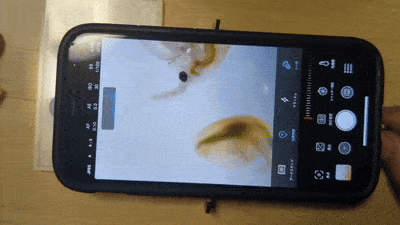
(ミジンコの観察)
身近にあるのに今まで見ることが難しかったミクロの世界の不思議。ミクロハンターはそんなワクワクする「小宇宙」をスマホで気軽に観察できてしまう秘密道具です。製品を通して、たくさんの感動と次なる好奇心が生まれる事を願っています。

(オシロイバナの花粉)

(ミドリゾウリムシの観察)
▼圧倒的な携帯性

専用ケースに全て収まり、財布にも収納可能。常に持ち歩けて、「観察してみたい」と思った瞬間を逃しません。
▼妥協のない光学設計

高度な技術を要する組み合わせレンズで、卓上顕微鏡にも匹敵する低収差と高解像度を実現。

ミクロの世界を本格的に楽しめて、趣味はもちろん仕事や教育にも幅広くご使用頂けます。
▼革新的な照明設計

スマホライトで観察が可能ですので、顕微鏡レンズ自体は充電や電池交換の必要がありません。

持ち運ぶものは最小限でコンパクト、スマホさえあれば顕微鏡観察が可能となります。
▼ほぼすべてのスマホに対応

革新的な吸着ナノパッドであらゆるスマホに装着可能。ケースを装着したままでも使用できます。

機種変更しても使い続けられるので、長くお使い頂けます。
▼組立式フォーカススタンド


専用ケースにも収まるフォーカススタンドを使えば、ピントの調整&固定が可能!(一部の商品では別売)
▼簡単な装着方法

コツさえつかめば、使い方はとても簡単。スマホにピタッと張り付けるだけで顕微鏡観察が可能です。
ミクロハンター製品で見るミクロの世界を通して、新たな探求心や感動が生まれていく事を願っています。
ミクロハンターレンズについて詳しくはページ下部のURLをご確認下さい♪








